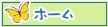最期のメロン
最期のメロン
母の死についての話である。
母は北海道の十勝平野に生まれた。
その後、いわゆる内地(本州)に渡って来たという。
越してきた時は近所の人から「北海道さん、北海道さん」と呼ばれていた。
今でも、私が生家の近くに行くと「北海道さん!」などと呼ばれる。
そこで父と出会い結婚。
私は4人兄妹の長男として生まれた。
父は病弱で、入退院を繰り返していた。
貧しい家計を切り盛りしながら、加えて戦後の物不足の中で、食うや食わずで両親は4人の子供を育てていた。
母は普段から健康で、病気ひとつしない健康優良児の見本みたいな人だった。
ある日、身体の不調など訴えたことのない母が仕事を休んだ。
病院に行くことを勧めたが、普段から健康な母は「大丈夫だから」と言って拒んでいた。
心配した父と私は、強引に病院に連れ出した。
「何とも言えませんが、ガンの疑いがあります」と医師は私たちに告げた。
当時中学生だった私は、それが何を意味しているのか分かっていた。
現在と違い、当時のガンは不治の病だったのである。
多感な時期にあった私は、にわかには信じられなかった。
愛犬ロンの失踪に続いて母の胃ガン。
私は目の前が真っ暗になった。
手術の日。
6時間に及ぶ大手術。
告知はしていなかった。
軽い胃潰瘍だと母には告げた。
「すぐに済むから・・・」と。
手術時間を悟られまいと、腕時計は勿論、医師に頼んで病院中の時計を4時間ずらせてもらった。
同室の患者にもお願いした。
麻酔からさめた母に、手術時間を短く見せるためである。
病弱な父に代って長男の私が手術に立ち会った。
「お幾つですか?」と医師は聴いた。
「15歳です」と答えると、「もっと年長のご家族はいませんか?」と医師。
しかし、医師の説得を振り切って私は手術に立ち会った。
初めて見る人間の内臓。
それも母の内臓である。
私の記憶ではガンの細胞は黄色かった。
数の子のような粒々が胃から胸へと転移していた。
医師は、開腹するなり私に淡々と説明した後、首を横に振った。
私は貧血を起こし、その場に倒れた。
医師は「あと3ヵ月です」と告げた。
今でも忘れられない、母の最後の言動が2つある。
最期のメロン。
点滴で持たせていた母の身体は、食べ物を受付けるような状態ではなかった。
しかし、「何が食べたい?」と聞いたら、何故か「メロン」と言ったのである。
12月31日、当時メロンなどは何処の店にも行っても売ってはいなかった。
私は探し回った。
そしてやっと見つけた。
すぐに病院に駆けつけた。
私は間に合わないと思っていた。
急いで下の妹にメロンを剥かせた。
ナイフで刺したメロンを口もとに差し出すと、不思議にも、切り分けたメロンを一口で食べたのである。
最期の水と言うが、母は「最期のメロン」であった。
そして、物を食べる母の姿を見たのはその時が最後である。
父に聞いた話だが、母の生家は北海道にいた時にメロンを作っていたというのだ。
死の間際で、生まれ育った遠い故郷を思い出したのだろうか。
おいしそうに食べた。
母が育てていたメロン。
それが夕張メロンだったかどうか、今となっては知る術もない。
以来、我が家では、命日には必ずメロンを仏壇に供えることにしている。
そして・・・最期の言葉。
それは母の右手の親指が放った。
医師は身体に悪いから、これ以上麻酔薬は打てないと言うのである。
何度もお願いをしたが聞き入れられない願いだった。
激痛をこらえながら、渾身の力を振り絞り、母は私に向かって親指を立てた。
「夫(私から見れば父)をよろしく!」との意味だとすぐに理解した。
自分がいま逝こうとしているのに、病弱な父を心配する優しい母であった。
手術からちょうど3ヵ月、医師の予言どおり、母は静かにこの世を後にした。
44歳であった。
これからという時であった。
あの貧しい中にあって、何もなかったが味噌で握ってくれたオニギリの味が、今でも忘れられない。
脳裏に焼きついている、お袋の味である。
私は既に母の年齢を超えた。
私は母のやり残したことを、形は違うがやり遂げようと思っている。
死の淵にありながら、なお人を気遣う母の姿。
その姿を今後の人生の指針として行きたい。
それは私にとって、知り得た全ての知人友人を気遣い、限りなく人を愛するという事に外ならない。